日本の伝統芸能とかを子供に触れさせたいと思っていたら、落語体験があったので、参加してみました。
落語は江戸時代から続く、日本の伝統的な話芸です。噺家が一人で何役も演じ、オチに向かって場面を盛り上げる独特の構成は、現代でも多くの人を魅了します。
しかし、時代背景の中で生まれた噺には、現代では「笑い」として受け止めにくい表現や描写も少なくありません。
今回は、そんな古典落語の一つ『牛ほめ』について、面白さと同時に感じた違和感、そして差別表現の問題を考えてみました。
落語とは
落語といえば笑点。子供の頃、祖父母の家に遊びに行くと祖父母の家のテレビには笑点が流れているイメージがありました。初期の漫才師は落語家出身というイメージがあるものの、能や歌舞伎といった伝統芸能というイメージもあまりなかったです。
落語口座で落語は江戸時代中期には整理した話芸と聞いてびっくりしました。調べてみたところ落語の発祥は以下の通り。
元禄期、京都では露の五郎兵衛が四条河原や北野などの大道(だいどう)で活躍した。これを「辻噺」といい、これを行った人々を「噺家」といい、落語家の始まりとされる[3]。五郎兵衛が机のような台に座って滑稽な話をし、ござに座った聴衆から銭貨を得るというものであった[5]。五郎兵衛は、後水尾天皇の皇女の御前で演じたこともあった。 ウィキペディアより
落語口座の中で和傘の上で毬を回す芸も紹介され、「あっこれって子供の頃正月番組で見た「いつもより多く回しております。」や!。これって落語の一種やったんや」と驚きました。
落語を見れる場所は「奇席」といい浅草等で見れるようです。そのような中、落語体験として紹介された噺が少し気になりました。
古典落語 牛ほめ(普請ほめ)
古典落語の一つ、元禄11年(1698年)には原型ができ、天保4年(1833年)にはほぼ現在の形となった古典落語。
与太郎という、少し抜けた若者が主人公です。父親から「親戚の新築祝いに行き、立派な牛を見たら褒めるように」と教えられます。
褒め言葉を覚えて訪問する与太郎ですが、場当たり的でズレたやりとりを繰り返し、最後は「屁の用心」という妙な褒め言葉で締めくくられ、観客は爆笑——という展開です。
話のテンポや言葉遊びの巧みさは、古典落語の魅力そのものです。
(牛褒めの詳細はこんな内容)
とにかく頓珍漢な言動ばかりしている与太郎。万事が世間の皆様とズレているので、父親は頭を抱えている。
今度、兄貴の佐兵衛が家を新築したと聞き、これは与太郎の汚名を返上するチャンスだと考えた父親は、家を褒めさせるため、与太郎に次の口上を伝授しようとする。
結構な御普請でございます。普請は総体檜造りで、天井は薩摩の鶉木目。左右の壁は砂摺りで、畳は備後の五分縁でございますね。お床も結構、お軸も結構。庭は総体御影造りでございます。
そこでさらに台所の柱に節穴があることを指摘した上で、そこに秋葉様の札を貼れば、火除けにもなって節穴も隠れると言えば、小遣いを恵んでくれるだろうと話す。与太郎がもっと何か小遣いがもらえるものがないかと尋ね、父親は伯父の飼っている牛を褒めろと次の口上も紹介した。
この牛は、「天角地眼一黒直頭耳小歯違」でございます。
「天角地眼-」というのは、菅原道真が寵愛した牛の特徴で、最高の褒め言葉だと説明する。
練習させると与太郎は天井を「薩摩芋に鶉豆」、「左右の壁は砂摺り」を「佐兵衛のカカァはおひきずり[注釈 2]」などと言う始末。やむなく紙に書いて与太郎に渡し、伯父の家に送り出した。
伯父のところにやってきた与太郎は、父親との練習通りに挨拶をすませて、隠し持った紙を読みながらではあるが、何とか口上を言うことに成功。
水を飲みたいと言って台所へ行き、節穴を見つけて、教えられたとおり秋葉様の札を貼るように進言、感心した伯父は1円の小遣いを渡す。そこで与太郎が牛小屋に出向いて「天角地眼-」とやっていると、牛が目の前で糞を落とした。「畜生だから褒めた人の前でも糞をする」という伯父に与太郎は、ここにも秋葉様のお札を貼ればという。
「穴が隠れて、屁の用心になる」
ウィキペディアより
面白さの本質
与太郎の頓珍漢な発言、落語家の話しぶりが面白く、子供にも理解でき、また子供たちにも笑いが伝わる落語入門としてはいい話だと思います。
・与太郎の“空回り”による笑い
・同じフレーズを繰り返すことで生まれるリズム感
・オチの予想外さと、間(ま)の取り方の妙
→噺家によっては、与太郎の仕草や表情を大きくデフォルメし、さらに笑いを膨らませるようです。
少し感じた違和感
牛褒めは与太郎の頓珍漢な発言が面白く、また「誰も傷つけない笑い」なのかもしれません。昭和末期から平成中期(後期か)はいい・悪いは別として「ダウンタウン」や「とんねるず」の笑い(いじり)が一世を風靡していましたが、令和に入ってからはそのような漫才は敬遠される風潮になったと思います。
ただよくよく考えるとおそらくこの「牛褒め(普請ほめ)」の主人公はおそらく軽度知的障害もしくは発達障害なんだろうなと思いました。
軽度知的障碍者(発達障害者かもしれませんが、一旦ここは軽度知的障害者/最近の言葉でいうとボーダー)の現実に即さない、くそ真面目な言動を面白おかしく、話して大衆・子供たちが笑う。
江戸時代ではそれが普通で誰も疑問に思わなかったのだろうと思います。いや昭和~平成中後期ですら許容されていた笑い。
ここで落語の伝統的な入門的な噺「牛褒め」を「障碍者差別だ!」と非難する気は一切ありません。ただなんとなく人間の「性」というものを感じて少しもやもやしました。
人間って難しい。子供の頃見て大笑いしていた「ホモネタ」とか「禿ネタ」も当時モヤモヤしている人もいたんだろうな。
笑いと差別の境界線を引くのは難しい
伝統芸能は、その時代の価値観や社会背景を色濃く反映します。古典落語の中には、女性蔑視、職業差別、障害者描写など、今では不適切とされる要素が散見されるのも事実。
『牛ほめ』は笑える噺である一方、その笑いの構造が特定の属性の人を笑いものにしていないか——それを意識することは、伝統を受け継ぐ上でも大切です。
ただこれを過剰に意識しすぎた結果が、テレビ離れ・息苦しい世の中になるのも事実。答えの出ない難しい問題だなと感じました。


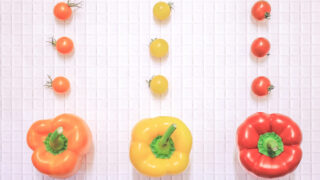

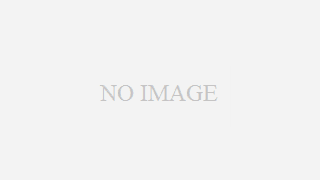

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b38508a.b00218e6.4b38508b.dbc809fc/?me_id=1278256&item_id=22662804&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F3236%2F2000013643236.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b38508a.b00218e6.4b38508b.dbc809fc/?me_id=1278256&item_id=25155214&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F0023%2F2000018110023.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

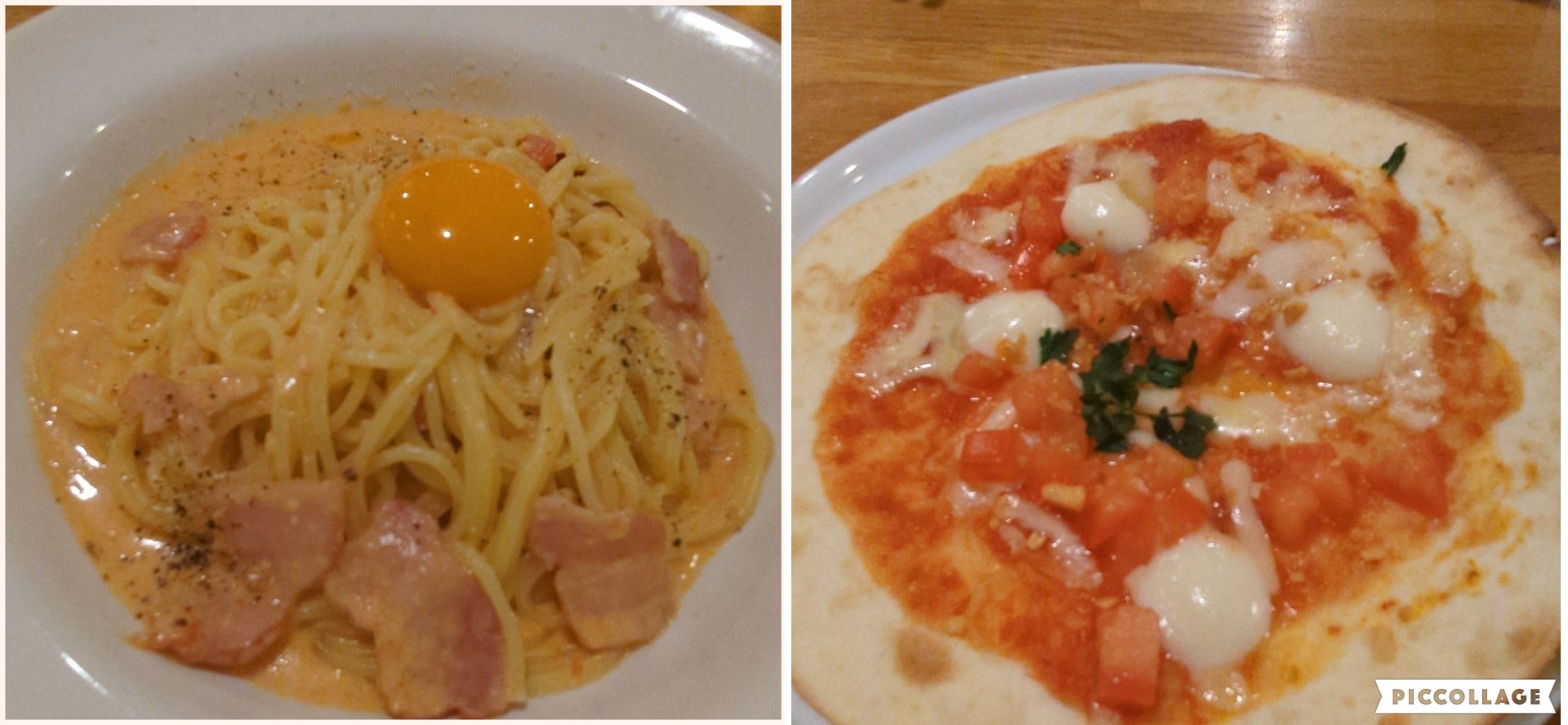
コメント