40代氷河期世代の悲哀。職場では「もう働きたくないパワハラ系おじいさん」と「静かな退職Z世代」に囲まれ、なぜか全部のしりぬぐいをする羽目に…。
思いのたけを込めたタイトルになってしまいましたが、この記事は職場で起きている「世代間ギャップ」と、それに振り回される私のような中堅社員の実情について綴ったものです。
私と同じように感じている人がいるのか、それとも私がルサンチマン(怨恨)に満ちているだけなのか。書きながら、自問自答しました。
働き方改革の陰で、誰かがしわ寄せを受けている
「もう限界かもしれないな…」
そんな言葉が頭をよぎることが最近多くなりました。
40代氷河期世代、現場の中間管理職。
上には“かつてのパワハラ上司”が再雇用で戻り、下には“静かに退職中”のZ世代。
そして隣の課では「女性活躍推進」の名のもとに、配慮だけされて実務はスルーされる上司。
そんな職場環境で、気づけば毎日、誰かのフォローと尻ぬぐいをしている自分がいます。
「働かないのに攻撃的」な元課長・Aさんの存在
私がいま頭を抱えているのが、元・パワハラ課長のAさん。
現役時代は机を叩き、大声で怒鳴るような“昭和スタイル”で、部下に恐れられていました。
そのAさんが、体調を崩したことを理由に早期で役職定年となり、現在は平社員として復職中。
しかし、現場ではまったく戦力にならず、それどころか「他人の仕事にはダメ出し」「自分のミスは隠す」など、対応に苦慮することばかりです。
たとえば──
- 担当業務を放棄し、周囲がカバーしても、その資料に文句だけは言ってくる
- 自らの不備で取引先に迷惑をかけたにも関わらず、課長や私が謝罪に行く羽目に
- 「扱いにくい人材をうまくマネジメントするのも係長の仕事」と、上司から突き返される
組織としても、ハラスメントのように明確な問題ではないため、なかなか手を打てないのが現実です。
今後、再雇用年齢の引き上げが進めば、こうした「扱いづらいベテラン社員」は増えていくのではないでしょうか。
企業はそろそろこの問題に真正面から向き合うべき時期に来ていると感じます。
隣の課は“静かな退職”と“配慮される管理職”のダブルパンチ
もう一つ、私の頭痛のタネになっているのが、隣の課のZ世代社員・Bさんと、その上司のC課長。
Bさんはいわゆる「静かな退職」状態。
指示された最低限の仕事はこなすものの、それ以上の関与は一切せず、周囲との連携も希薄です。
先日、全体で共有された報告業務の変更について、私の課はすでに対応済み。
隣の課は未対応だったため、Bさん宛に注意喚起の連絡をしたところ、返ってきたのはこんな返信でした。
「この業務はもう私の担当ではありません。Dさんにお願いします」
そのメールには上司のC課長もCCに入っていました。
普通なら課内で連携を取り、後任に引き継ぐものですが、返事はなく、最終的にミスの修正依頼が私のもとに届くことに。
C課長はというと、育休による時短勤務のためすでに退勤済み。
結局、私はよくわからない隣の課の報告資料を、手探りで修正対応することになりました。
「配慮」と「甘やかし」は違うと思う
後日、グループ長に苦情を伝えると、こんな返答がありました。
「確かに対応ありがとう。でもメールの文面にトゲがあって、パワハラにはならないけど、気をつけてね」
正直、力が抜けました。
ちなみにそのグループ長は、私が新人の頃に同期をうつ病に追い込んだ元・パワハラ係長。
そんな人が今、人事部からの「働きやすい職場づくり」という通知を片手に指導してくるのです。
「多様な働き方」だけでなく、「最低限の責任」も定義してほしい
時短勤務、静かな退職、再雇用制度──
どれも働き方の多様性を認める、大切な制度です。
しかしそれらを成立させるには、「最低限、果たすべき責任のライン」を明確に定義する必要があるのではないでしょうか。
制度は整った。
でも、現場ではしわ寄せが特定の層に集中している。
それが今の職場のリアルです。
最後に:私たちは“便利屋”じゃない
私はただ、効率よく仕事を回したいだけなんです。
でも今の職場では、誰かが仕事を放棄するたびに、それを拾い、整理して、関係者をなだめて…
気づけば、自分の本来の業務は後回しになっています。
働き方改革の“理想”が、“中間世代の消耗”の上に成り立っているとしたら、あまりに不健全ではないでしょうか。


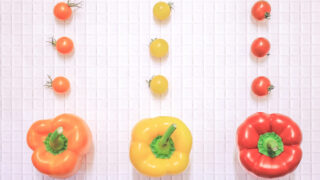

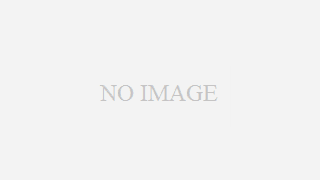
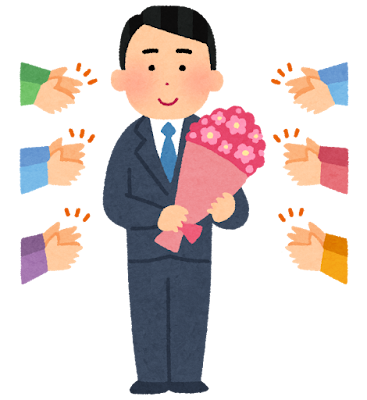

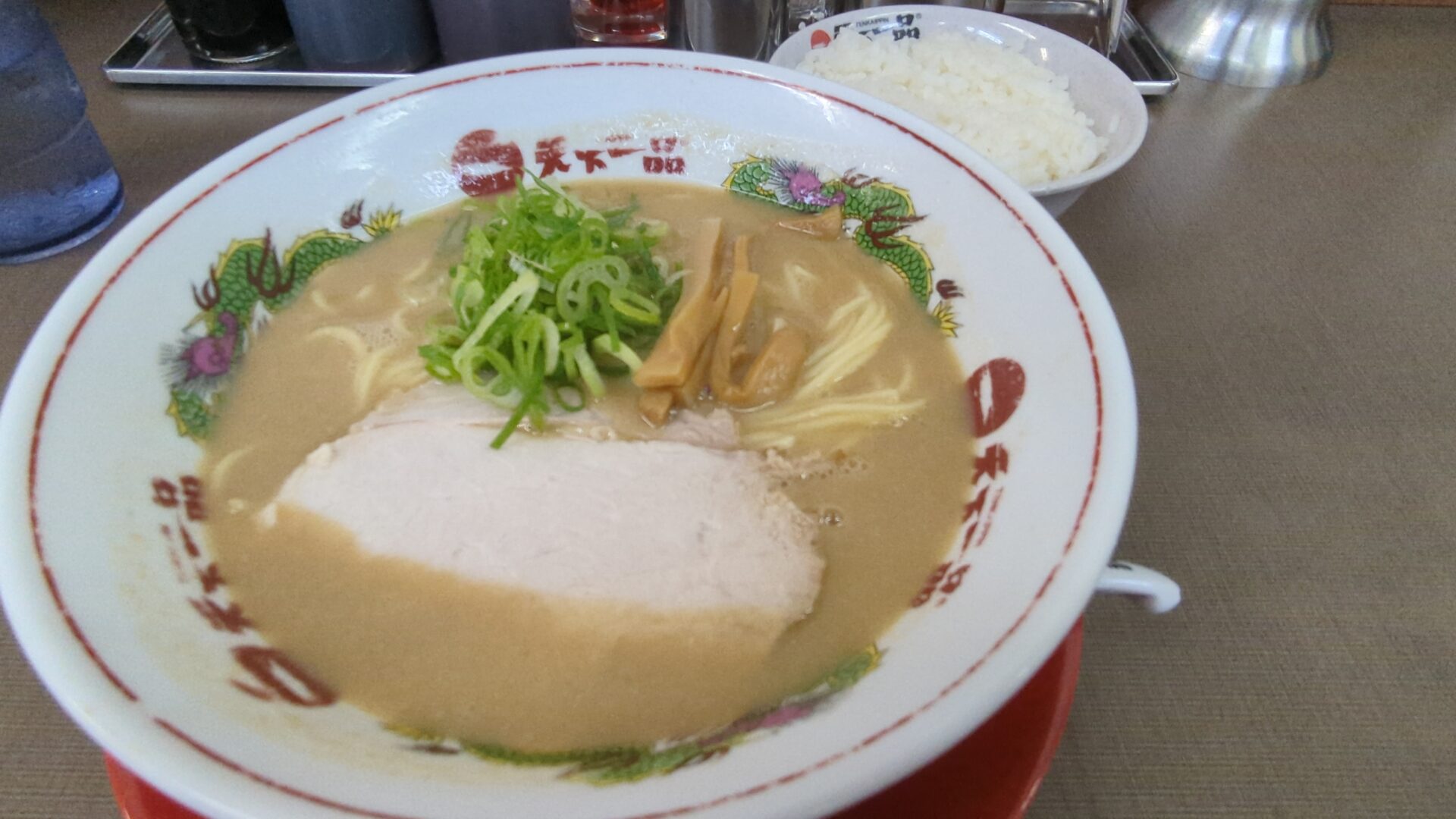
コメント