サピエンス全史の上巻を読んでから1か月以上時間がたってしまいましたが、ついに下巻を読破しました。これほど有名な本の中身はもっと詳しい人に任せるとして、今回は私たち夫婦が現代社会の常識がいかに不安定な土台の上に成り立っているかを知って驚いた点に焦点を当てて感想を書き綴ります。
誰もが信じる「進歩」という信仰の起源
下巻は、上巻の認知革命の続きとして宗教の話(精霊信仰、多神教、一神教)から始まりますが、特に現代に決定的な影響を与えているのが、中盤から始まる「科学革命」の話です。
我々が現在、疑うことなく持っている常識——「未来はもっとよくなる。過去よりも明るい未来がある。そのために頑張ろう」——この考え方が、実は科学革命の結果生まれた認知の変化にすぎなかったという事実を知り、深く驚かされました。
「科学革命」以前、人類の文化は「進歩」というものをほとんど信じておらず、黄金時代は過去のものであると考えていたのです。
たとえば、日本にも根付いている儒教は、太公望などが登場する周の時代の礼節をたたえる復古主義的な考え方です。科学革命以前は、未来が今よりもよくはならないだろうと考え、その代わりにあの世でいい暮らしをしようという宗教的な考えが一般的でした。
つまり、「努力すれば未来は明るくなる」という私たちの社会の根幹をなす信念は、人類の歴史全体から見ればごく最近の流行であり、科学革命という歴史的な転換によって後天的に植え付けられたものにすぎないのです。
科学革命の核心:「無知の発見」こそが人類を飛躍させた
では、なぜ「進歩」という概念が生まれたのでしょうか。
人類が「進歩」を信じ始めたのは、科学による発見が私たちに途方もないほどの新しい力をもたらすとわかったからです。
近代科学の最大の革命性は、単に知識が増えたことではありません。それは「無知の革命」なのです。
西暦1500年ごろまで、世界中の人々は新たな能力を獲得できるとは思っておらず、持っている能力をいかに維持するかに心血を注いでいました。しかし近代科学は従来の知識の伝統とは次の3つの点で決定的に異なっています。
1. 進んで無知を認める意志:私たちはすべてを知っているわけではないという前提に立ち、いかなる概念も神聖不可侵ではないとします。
2. 観察と数学が中心:無知を認めたうえで、観察結果を収集し、数学的ツールを用いて包括的な説にまとめ上げます。
3. 新しい力の獲得を志向:理論を生み出すだけでなく、特に新しいテクノロジーの開発という新しい力の獲得を目指します。
つまり、人類は自らにとって最も重要な疑問の答えを何も知らないという重大な発見、この「無知の発見」こそが、科学研究に資源を投入し、新しい能力を高められると信じる大きな流れを生み出したのです。
解決不可能と思われた問題が科学の力で次々と解決し始めたのを見て、人々は新しい知識を獲得・応用すれば、どんな問題でも克服できると自信を深めました。
「飽くなき成長」を求める社会の構造が見える
この「進歩」への信仰は、近代経済の構造とも深く結びついています。近代経済は飽くなき成長を求める構造を持っており、進歩を信じ始めた人々は、未来の成長を当てにして「信用(クレジット)」にもとづく経済体制を確立しました。
さらに重要なのは、科学は純粋に独立した営みではないというハラリの指摘です。科学は非常に費用がかかるため、経済的、政治的、イデオロギー的な干渉を受けています。科学研究は、その優先順位や発見した事象をどうするのかを自ら決めることはできず、宗教やイデオロギーと提携した場合にのみ、うまく栄えることができるのです。
科学の発展を理解するには、物理学者や生物学者の業績だけでなく、それを特定の方向に進ませた帝国主義と資本主義という力も考慮に入れなくてはならない、という洞察は、まさに下巻で最も深く考えさせられる部分でした。
まとめと感想 現代を生きる私たち
下巻は、上巻ほど「え~~!」という驚きの瞬間はなかったかもしれませんが、現代人が日々直面する、「常に成長し続けなければならない」という現代社会のプレッシャーや構造的な期待が、いかに歴史的に浅い「認知の変化」にすぎないかを理解させてくれます。
私たちは無意識のうちに「未来は良くなる」という教義を信じていますが、この本は、その信仰がどこから来て、どのような権力(資本主義や帝国主義)と結びついて機能しているのかを鮮やかに描き出しています。
ぜひ、上巻に引き続き、この「文明の構造と人類の幸福」というテーマを扱った下巻を手に取ってみてください。


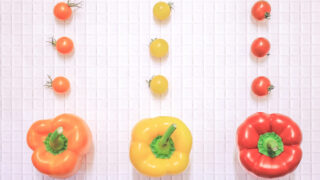

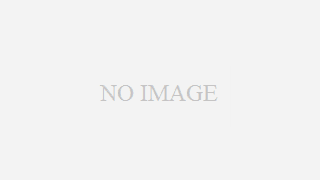
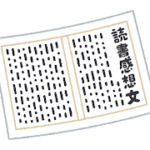

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/195c53f6.a2f5700d.195c53f7.28931dcd/?me_id=1213310&item_id=21070423&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7894%2F9784309467894_1_5.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)



コメント