ダニエル・キイス著の「アルジャーノンに花束を」を読んだ。
山Pやユースケ・サンタマリアが主演で日本でドラマ化もされたSF作品。
私はユースケ・サンタマリア主演のドラマを過去に一度見たことがあるだけだったので、
原作を手に取って読んだのは初めてだ。
大まかな流れ・骨子としては6歳程度の知能しかもっていない知的障碍者チャーリーが手術を受けて
知能・IQの向上を果たし、天才となる。
知能・IQの向上により、仲間だと思っていたパン屋の人たちは自分を馬鹿にしていたこと等を知り、
また知能の発達に心の成長が追い付かず、周囲の研究者等と軋轢を生む。
過去のおぼろげながらの記憶を頼りに父・母・妹との再会等をへつつ、急激な知能の発達が
知能の低下をもたらす事実を知る。
知能の低下の恐怖に慄きながら、自らを取り戻していき、最後は障害者施設へと自ら向かうところで話は終わる。
なお、題名のアルジャーノンとはチャーリーの知能向上手術の前に実施された動物実験のネズミの名前。アルジャーノンの知能の後退をきっかけに、チャーリーも知能向上手術が一時的なものであった(失敗であった)ことを知る。
原作はチャーリーの実験での自らの変化を記した「経過報告」形式で書かれているので、基本的には主人公チャーリーの一人称目線。
6歳程度の知能しかなかった頃のチャーリーの経過報告部分はひらがなが多く、誤字・脱字も多い(わざとそうしている)ので、正直、読みづらいものがあった。
しかし知能の低下を知ってからのチャーリーの経過報告が徐々に稚拙になっていく様子はある意味ホラーといってもいいのかもしれない、底知れぬ恐怖を感じた。
SF作品ながら、SF部分は「知能を向上させる手術」のみであり、それ以外は日常の記載なのも新鮮。
読後感想としては、ありきたりな表現ながら何とも言えない気持ちになった。
私自身を翻ってみると「鬱病」で休職中。自分自身の姿とチャーリーを重ね合わせてみていたような気がする。
知能が向上し天才となったチャーリーが知能向上は一時的なものであることを知った絶望・今まで読めていた本が読めなくなる悔しさは身に染みて感じた。
今まで普通に会社に行ってそれなりの書類を起案していたのに、今は社会から隔離され休職中の自分自信に投影してしまった。
考えれば人間は年老いていくにつれできていたことができなくなっていく。チャーリーの出来事は人間が老いていく中で追体験をするのかもしれない。




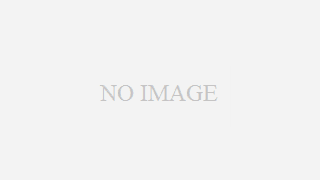



コメント